AIが提案する「改革」には、重大な欠落がある
現代は、データさえあれば何でも最適化できると思われがちな時代です。「この会議は無駄です」「この書類作成作業はコストの割に成果が見合っていません」。AIによる分析は、冷徹なまでに私たちの社会から「非効率」を削ぎ落とそうとしています。
確かに、無駄を省くことは大切です。しかし、歴史好きの視点から見ると、少し背筋が寒くなる瞬間があります。「その『無駄』こそが、実は社会を支える大黒柱だったらどうするのか?」という懸念です。
一見すると意味のなさそうな慣習や、古臭いしきたり。それらを「現在の視点」だけで断罪して撤去してしまった結果、取り返しのつかない崩壊を招いた事例は歴史上枚挙にいとまがありません。
今回は、イギリスの作家G.K.チェスタトンが提唱した思考実験「チェスタトンの柵」を補助線に、江戸時代の「天保の改革」がいかにつまずいたのか、その本質を深掘りしてみましょう。
「チェスタトンの柵」とは何か?
本題に入る前に、この概念を共有しておきましょう。チェスタトンは著書の中で、ある道路に立っている「理由のわからない柵」を例に挙げています。
あるとき、改革者はこう言います。
「この柵が何のためにあるのか分からない。邪魔だし、現代の私たちには利用価値が見えないから撤去してしまおう」しかし、これは愚かな改革者です。賢明な改革者はこう考えます。
「この柵がなぜここに置かれたのか、その『建設理由』が判明するまでは、決して撤去してはならない」
つまり、古いものがそこにある以上、過去のどこかの時点では「置かざるを得ない理由」があったはずなのです。それが安全のためなのか、境界線のためなのか、あるいは宗教的な意味なのか。その「創業の精神」や「設置の経緯」を理解しないまま、現状の数値効率だけで撤去すると、後で痛い目を見るぞという警句です。
AIは現状のデータ分析は得意ですが、数百年前にそのルールが作られた「歴史的文脈」までは読み解けません。ここから紹介する水野忠邦も、まさに優秀すぎるがゆえに「柵」を撤去してしまった人物でした。
水野忠邦が撤去した「江戸の柵」
江戸時代後期、幕府の財政は火の車でした。第12代将軍・徳川家慶のもとで老中首座となった水野忠邦は、財政再建のために断行した「天保の改革」で知られています。
忠邦は非常に頭の切れる人物でした。彼が目をつけたのは、江戸の町に溢れる「贅沢」と「娯楽」です。当時の江戸は町人文化が爛熟し、人々は華やかな着物を着て、歌舞伎や寄席(よせ)に通い、美食を楽しんでいました。
忠邦の計算は論理的です。
「人々が娯楽や贅沢に使っている金が無駄である。これを禁止し、質素倹約を徹底させれば、浮いた金が蓄えられ、また農村へ人が戻り、幕府の財政基盤である米の生産量も上がるはずだ」
現代のAIコンサルタントなら、「娯楽費を100%カットし、労働生産性の高い第一次産業へ人員を再配置しましょう」と提案するようなものです。非常に合理的で、数字の上では完璧な計画に見えました。
「無駄」こそが経済のエンジンだった
忠邦は実行に移します。寄席の閉鎖を命じ、歌舞伎役者を江戸の中心部から浅草の場末へと追放しました。華美な着物は禁止され、菓子や子供の玩具に至るまで「贅沢品」として規制の手が入ります。
ところが、結果はどうなったか。景気が良くなるどころか、江戸の経済は急激に冷え込み、大不況に陥ってしまったのです。
なぜでしょうか。忠邦が「無駄な柵」だと思って撤去した「贅沢」こそが、実は江戸の経済を回す巨大なエンジンだったからです。
- 着道楽がいるからこそ、呉服屋や染物屋が潤い、地方の織物産地にお金が落ちる。
- 食道楽がいるからこそ、農村の特産品が高値で売れる。
- 芝居小屋があるからこそ、その周辺の茶屋や土産物屋で雇用が生まれる。
これらすべてを「非効率な浪費」として禁止した結果、金の流れ(マネーストック)が完全にストップしてしまいました。商人は売上が立たずに倒産し、職人は仕事を失い、結果として幕府への運上金(税金のようなもの)も減るという悪循環。
忠邦が見落としていた「柵の理由」とは、「一見無駄に見える消費行動が、複雑な相互依存関係の中で社会全体の富を循環させている」という事実でした。
AIには見えない「生存バイアス」の正体
これを現代のAI論に置き換えてみましょう。AIは「目的関数」を設定すれば、最短ルートを弾き出します。しかし、その目的関数が「短期間でのコスト削減」に設定されていた場合、数百年かけて形成された「見えざるセーフティネット」までコストとして計上し、削除推奨リストに入れてしまう恐れがあります。
例えば、日本の企業によくある「朝礼」や「飲みニケーション」、あるいは地域社会の「面倒な祭り」。これらはタイパ(タイムパフォーマンス)の観点からは最悪です。
しかし、これらの慣習が数十年、数百年と続いてきたことには「生存バイアス」的な理由があるはずです。
それは、普段からのゆるい繋がりが緊急時の相互扶助を可能にしていたり、非言語的な情報の共有によって組織の価値観が統一されていたりと、数字には表れない機能を持っていることが多いのです。
「伝統的に続く慣習」は、過去のあらゆるトラブルや環境変化を生き延びてきたという実績そのものが、一種の証明書になっています。その証明書の中身を解読せずに、ただ「古いから」「非効率だから」といって破り捨てるのは、あまりにもリスクが高い行為です。
「わからない」を尊重する姿勢
水野忠邦は改革の失敗により、わずか2年ほどで失脚しました。江戸の庶民は彼の屋敷に石を投げ込み、失脚を祝って大いに騒いだといいます。
私たちがAIを活用する際、AIが「この慣習は無駄です」と指摘してきたら、一度立ち止まるべきです。「AIがそう言うのだから間違いない」ではなく、「AIには理解できない、人間特有の、あるいは歴史的な『柵の理由』がここにあるのではないか?」と。
その理由を探り当て、それが現代には本当に不要だと確信できたとき初めて、私たちはその柵を撤去する権利を得るのでしょう。歴史は、「わからないもの」に対して敬意を払うことの重要性を、繰り返し教えてくれているのです。











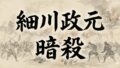

コメント欄 [スレッド上限:5階層]※暴言や過激な表現は伏字で